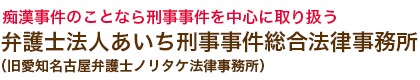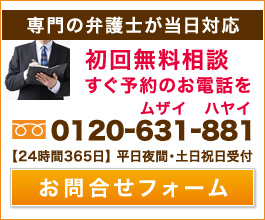【事例解説】電車内での痴漢事件を否認している事例➁
電車内での痴漢事件を否認している事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
神奈川県内の会社に勤めるAさんは、通勤中の電車内で突然見知らぬ女性Vさんに腕を掴まれ、痴漢を疑われました。Aさんとしては全く身に覚えがなく、違うと必死に訴えたものの周囲の人にも取り押さえられ、結果的に次の停車駅で降ろされ、駅員室に連れていかれることになりました。その後、通報によって現場に駆け付けた警察によってAさんは逮捕されることとなりました。
Aさんの妻Bさんは、会社からAさんが出勤していないとの連絡を受け、Aさんに連絡を取りましたが、音信不通でした。
Bさんは、Aさんが何か事件や事故に巻き込まれたのではないかと考え、警察に相談したところ、警察から「事情は言えないがAさんは今現在逮捕されている」と伝えられました。
そこで、Bさんは弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
【痴漢で前科が付くことを回避するには】
今回の事例では、弁護士が初回接見に行っています。
この初回接見では、具体的には、弁護士が取り調べについてのアドバイスを行います。
逮捕中には、捜査機関から取り調べをうけ、その内容が供述調書というかたちでまとめられ、それが裁判の証拠となります。
もしも自身に不利な供述調書が作成された場合、裁判で覆すことは非常に困難といえます。それゆえにそのような供述調書が作成されないように、取り調べに対してどのように対応するかを考えておく必要があります。
もっとも、どのような供述をすればよいかの判断を、法律の専門家でない方が行うことは非常に困難であるため、初回接見を利用することで弁護士からアドバイスをもらうことが得策です。
また、初回接見後に正式に弁護人として選任された場合、まずは早期の身体解放を目指します。逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこで、これを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。